外来で、「生きる意味」に悩み苦しむ患者さんのお話を聞きました。
色々考えさせられたので、記録に残そうと思います。
その患者さんは、物心ついた頃から、
・生きる意味・目的ってなんだろう
・生きていても、死んでいてもあまり変わらないのではないか
・他の皆は、生きる意味について考えずに、どうして平穏に暮らしていられるのか
などと考えて苦しむ方でした。
そのことを考えて苦しくて苦しくて、自殺を考えてしまうのです。
自分も高校生になったあたりから「生きる意味」について考えるのは好きで、友達と議論したり、哲学書を漁ったり、自分で考えたりしながら今日まで生きてきました。そもそもそういうことを考えるのが好きだから精神科に興味があるのであり、自分のライフワークと言っても過言ではありません。
今回、人は以下の3つに分類できると、改めて考えました。
- 「生きる意味」についてそもそも考えたり悩んだりしない人
- 「生きる意味」について考えたり悩んだりするが、それによって苦しまない人
- 「生きる意味」について考えたり悩んだりして、それによって苦しむ人
若い頃は漠然と、「生きる意味」と向かい合うことは辛いことであり、なるべくそれを考えないようにすることが大事と、考えていました。従って、あまりに暇な休日など、その議論に取り憑かれてしまった日などは、結構苦しんだりもしました。しかしある年齢から、「生きる意味」と向き合い、気持ち良いこと・楽しいことをすることが生きる意味だ、とか、他人のために役立つことをたくさんするのが生きる意味だ、とか、いやいやそれらは全部偽善で生きる意味なんて無いんだ、と時によって色々な結論が出ますが、どのような結論に辿り着いても特に苦しまなくなりました。苦しまなくなった理由として、ひとまず以下の2つの理由が思いつきました。
まず1つ目は、「生きる意味」についての議論は、とても難しい問題で、人類の長い歴史で多くの偉人が取り組んできたにもかかわらず、確たる正解が得られていない中で、自分の中ですぐにその答えが手に入らない状態が、特別変なことだとは思わなくなったからだと思います。さらに、そこから開き直って、これを考えることをライフワークにしてしまって、自分一人の問題というよりかは、社会全体の問題として捉えることで、この問い自体と自分を同一化しないようにすることに成功したのだと思います。
次に2つ目は、ありきたりになってしまいますが、人生を楽しむ術を、偏りなく身につけてきたからだと思います。社会人になって自分で稼げるようになり、家族・友達を大事にして、趣味も大事にして、そういったありきたりな幸せを、謙虚に偏りなく大事にする姿勢が、歳をとるごとに身についてきた気がします。若い頃はもっと穿った考えでもって、ありきたりな幸せを嫌悪したりするところがありましたが、丸くなったのか最近はなくなりました。「中庸」の考えが身についたのかもしれません。このような変化によって、「生きる意味」が分からなくとも、明日からも楽しく知的な日々が待っていると思えるから、そこまで困らないという状態です。
「生きる意味」の問いにたどり着いてしまう人は、マズローの考え方を借りると、基本的な身の安全や生存が保証されている人たちです。飢えに苦しむ人は、おそらく辿り着けません。それでもマズローの考えに賛同しきれないのは、飢えに苦しまない人はいないと思いますが、「生きる意味」の問いに苦しまない人は多く存在すると思うところです。その欲求をうまく転化させて別で満たしているだけなのかもしれませんが。とすると転化の技術の問題なのでしょうか。
思考が散らばってきたのでこのあたりで一度筆を下ろします。
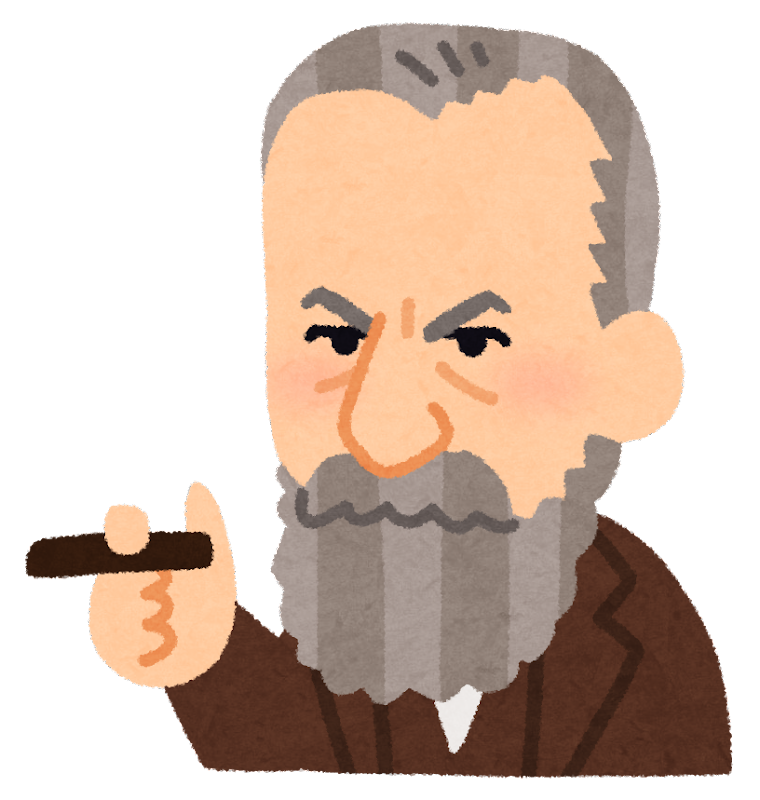
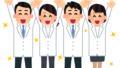

コメント