人は、実際に見たモノを記憶として脳内に蓄え、またそれを画像としていつでも脳内に呼び起こして描く能力を持っているが、実際に見ていないモノですら脳内に描く能力を持っており、それを妄想と呼ぶことにしよう。空想・幻想・想像などを含めた、広い意味での脳内で創造された画像や映像のことである。
また、人は、刻々と移り変わる目の前の状況に対し反応し、様々な感情を経験しながら毎日を過ごしているが、今目の前で起きていることのみならず、過去の記憶に対してでも感情で反応することができる。過去の楽しい出来事を思い返し、その時の映像を脳内に描けば、やはりその時と同じような気持ちになるし、もちろん不快な記憶に対しても同様である。
さらに人は、自分の妄想に対しても感情で反応することができる。
誰かに嫌なことを言われ、その瞬間に嫌な気持ちになったとしよう。家に帰ってその時のことを思い返し、また同じ嫌な気持ちになる。さらに、また明日同じことを言われるかもしれないとか、他の人にも言われるかもしれないなどと妄想し始め、その妄想に対してさらに嫌な気持ちになることができる。実際に起きたことでも、実際には起きていないことでも、一度脳内に描いてしまえば感情は同じように反応してしまうのである。
二次被害とでも呼べる妄想からの攻撃は、自分で作り上げた妄想からの被害なのだから、やろうと思えば自分でコントロールできるように思ってしまうが、思った以上に自分でコントロールすることができないというのが実際である。妄想の体系は、本能や後天的に獲得した知識などから成り立っていて、そのルールに従って自動的に展開されるから、中々自分で制御できないのである。それをどうにか自分でコントロールしようと試みたのがブッダであり、その方法が瞑想である。
正確に言うと、ブッダは実際に目の前で起きていることや、その記憶に対する感情の反応ですら妄想と喝破し、瞑想の対象としているが、それは中々辿り着き難い領域であり、まずは実際に起きたことではない部分、自分の脳内で作り上げた妄想への感情的な反応をコントロールすることを目指したい。
ただ難しいことに、妄想し、それに対し感情で反応する能力は、一概に悪とは言えないのである。海外旅行にワクワクできるのは妄想に感情で反応する能力のおかげだし、発明家や起業家の行動力の源泉も、やはり妄想力といえるからである。だから、不快で無益な妄想への反応だけをうまくコントロールできるようになりたいところである。
瞑想はモグラ叩きの精度を上げていくような作業だと思っている。妄想が生まれなければそれに付随する感情は生じ得ない。だから妄想が生まれた瞬間に、その妄想に「気づき」、そこで止める。「気づく」のが早ければ早いほど、妄想が鮮明なイメージを伴う前に止められるから、止めることに抵抗や痛みを伴いづらい。それを毎日毎日繰り返し、精度と早さを高めていく。このモグラ叩きを極めると、そもそも妄想が生じなくなるとブッダは言ったようだが、それがどのような領域なのかは正直よく分からない。
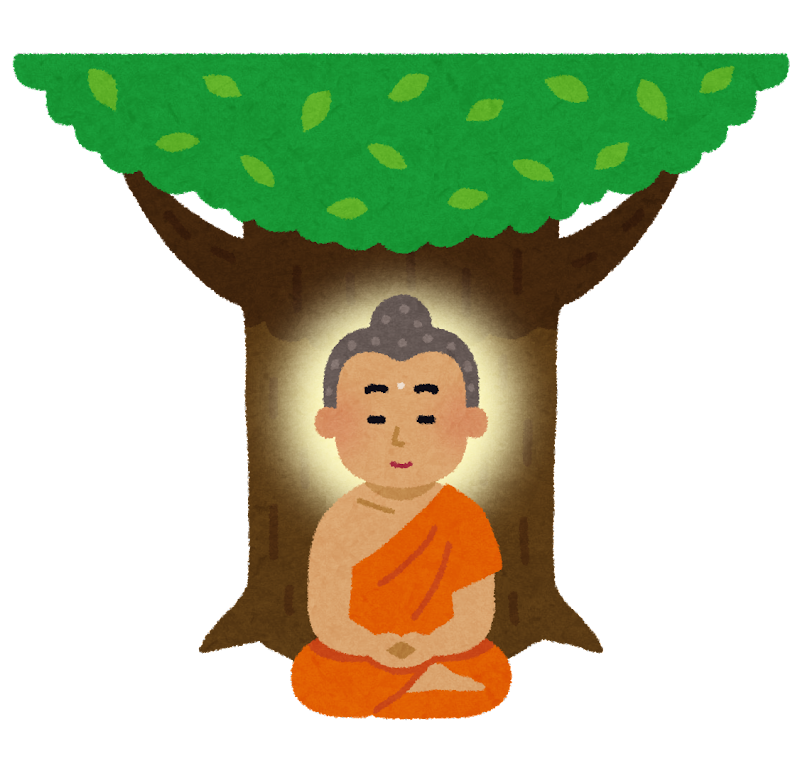



コメント